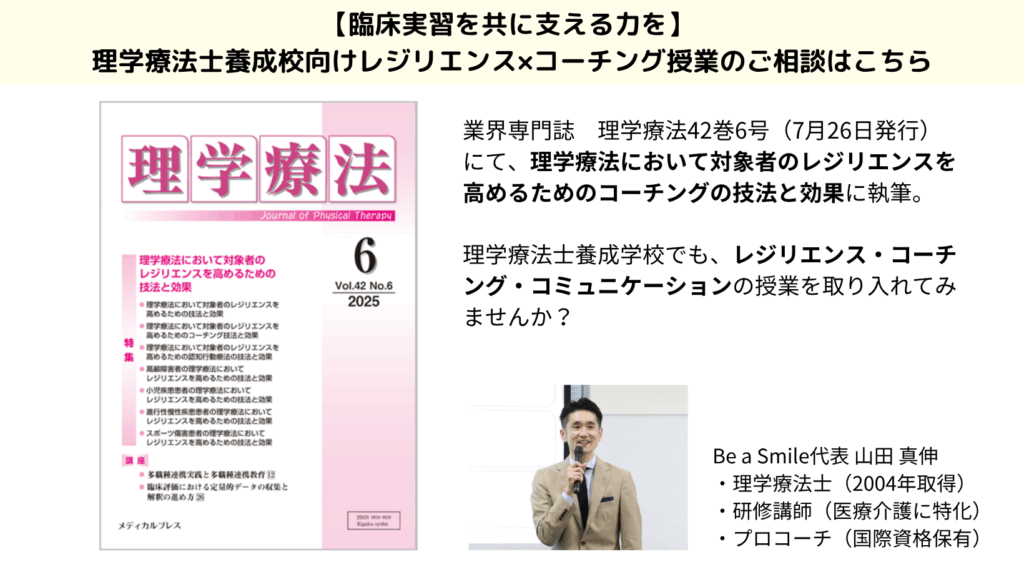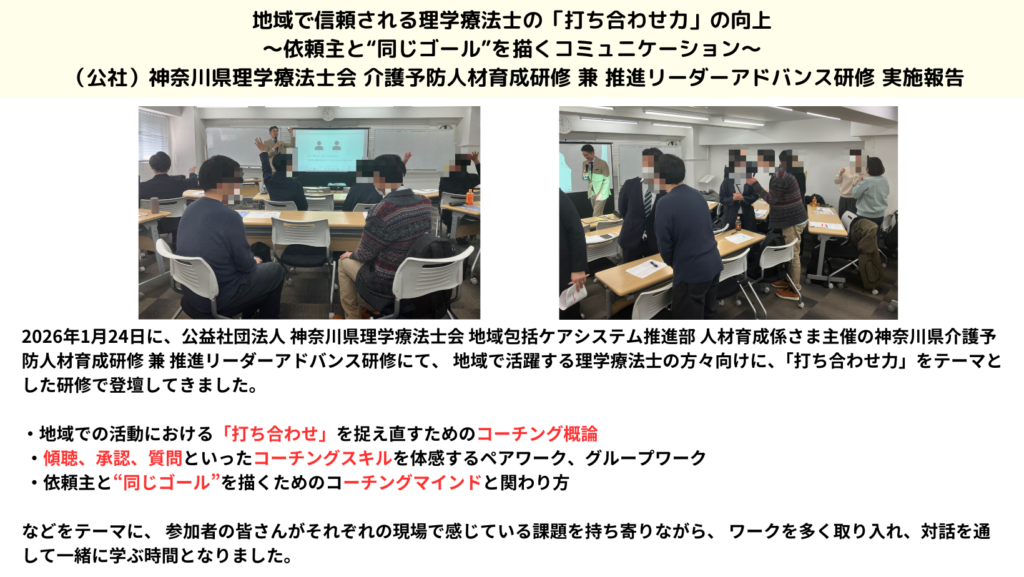理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)として、チームをまとめる立場に立つと、スタッフや後輩との関わり方に悩む場面が増えていきます。
その中で注目されているのが「コーチングスキル」です。
傾聴、承認、質問、フィードバック。
これらのスキルを身につけることで、スタッフとの関係性や多職種連携、さらには患者・利用者との関係までが円滑になりやすくなります。
スキルだけでは、人は動かない
しかし、忘れてはならないことがあります。
「スキルさえあれば人間関係がうまくいくわけではない」ということです。
研修講師としてコーチングスキルをお伝えする際、私が必ずお伝えしているのは、
「スキルよりも大切なのはマインドです」
という考え方です。
コーチングマインドの中には、
「その人の中に答えが存在する」
という大切な前提があります。
「その人の中に答えがある」マインドが、関わりを変える
このマインドを持って関わると、相手に興味関心を持つことが自然とできるようになります。
その結果、
- 話を傾聴できる
- 小さな努力を承認できる
- 相手の考えを引き出す質問ができる
- 成長を支えるフィードバックができる
といった行動が、無理なく生まれます。
一方で、「この人には答えがない」「教えなければ動かない」と思ってしまうと、
どうしても一方的な指導や指示になりやすく、
傾聴も承認も質問も、すべて“上から目線”になってしまいます。
つまり、マインドがスキルの質を決めるのです。
学術的背景:自己決定理論とロジャーズの視点
この考え方は心理学的にも裏付けられています。
たとえば、自己決定理論(Deci & Ryan, 1985)では、人が自発的に行動するために必要な3つの基本的欲求として、
「自律性」「有能感」「関係性」が挙げられています。
リーダーが「その人の中に答えがある」という前提で関わると、
スタッフは“自分で考えて行動できる”感覚(自律性)と、
“自分にもできる”という感覚(有能感)を得られ、結果としてチームのエンゲージメントが高まります。
また、カール・ロジャーズの来談者中心アプローチにおいては、
「無条件の肯定的関心(unconditional positive regard)」が、人の成長を支える重要な要素とされています。
これはまさに、コーチングマインドの核となる「興味を持つ力」に通じる考え方です。
現場でできる小さな一歩
コーチングマインドを実践するために、まずできることは、
「なぜこのスタッフはそう感じているのだろう?」
「何を大切にして働いているのだろう?」
と“相手の背景”に興味を持って質問してみることです。
それだけで、相手の表情や言葉が変わります。
そして、リーダー自身も「支える」姿勢に戻ることができます。
スタッフを“変える”のではなく、“理解する”。
そこからチームの関係性は確実に変わっていきます。
リーダーとしての原点は「興味関心」
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士として働く私たちは、常に“人と関わる専門家”です。
だからこそ、スタッフや仲間に対しても、興味を持ち続ける力が求められます。
コーチングマインドは、誰かを変えるための技術ではなく、
相手を信じ、成長を見守る“関わり方の姿勢”そのもの。
スキルを超えて、マインドでチームを動かす。
それが、これからのPT・OT・STリーダーに求められるリーダーシップの形です。
📘 関連記事
👉 ご感想やお問い合わせはこちらからどうぞ。
お問い合わせフォームへ
#理学療法士 #作業療法士 #言語聴覚士 #リーダーシップ #コーチング #チームビルディング #研修講師