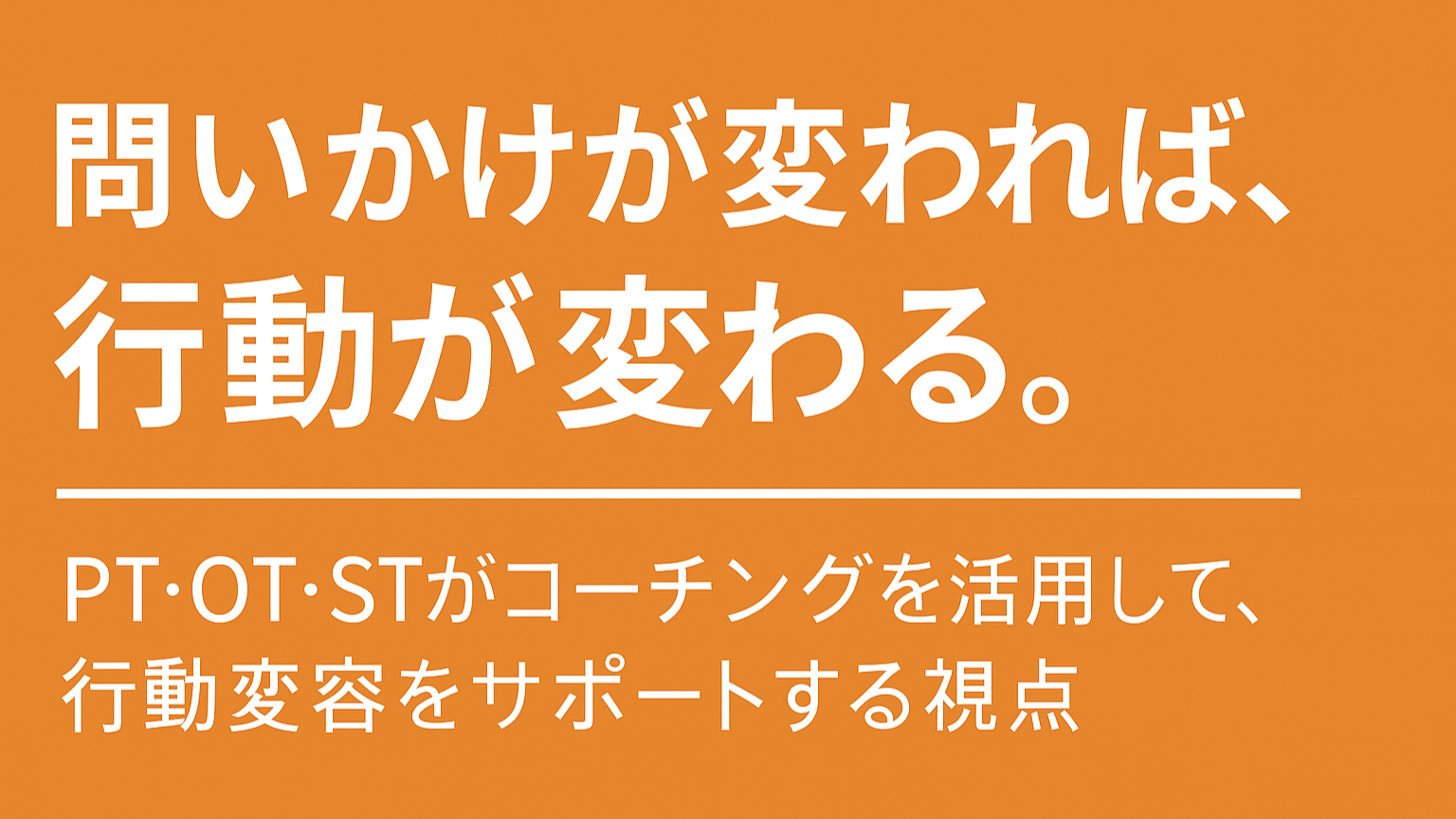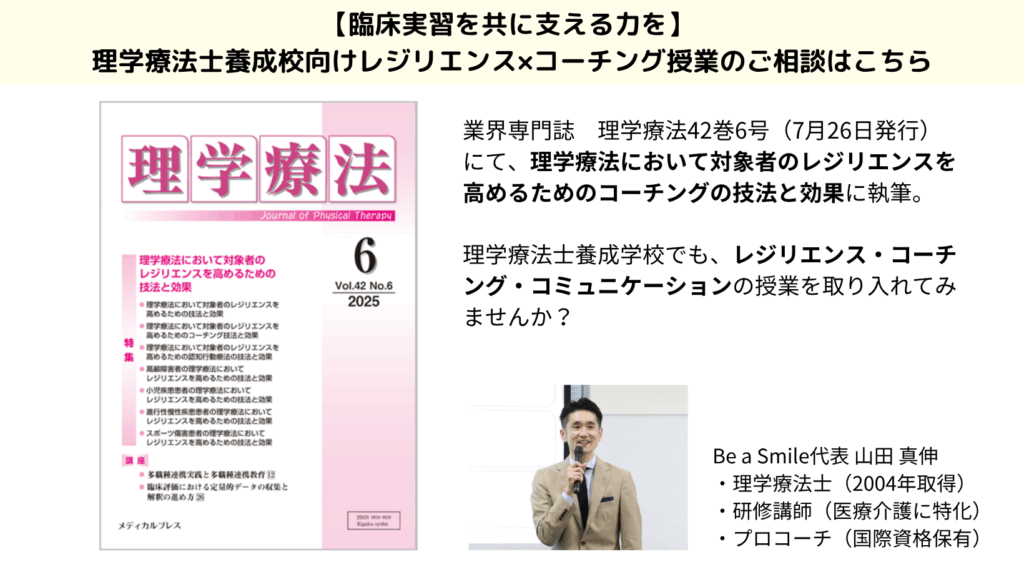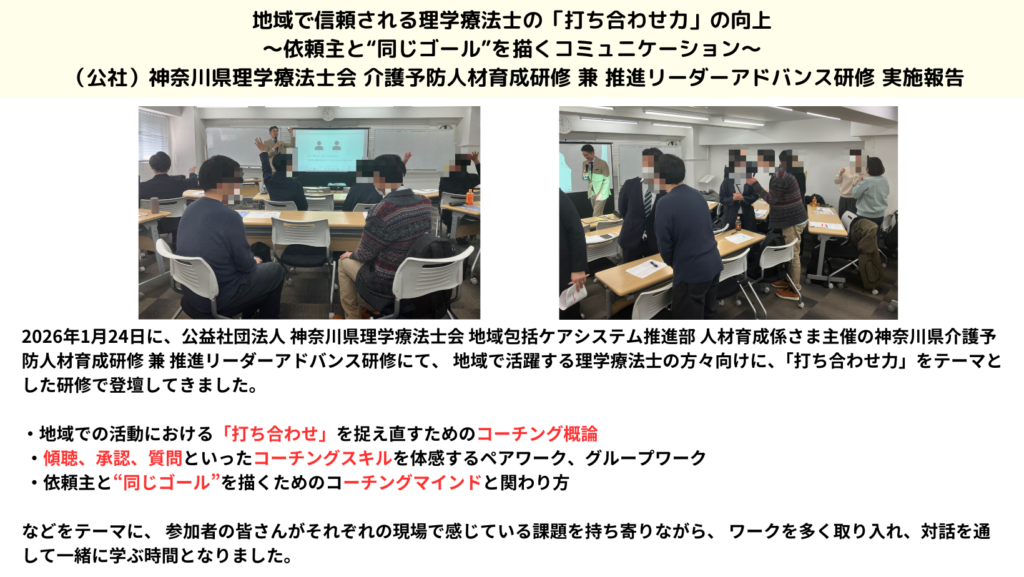「行動変容」。
これは、私がコーチとして、そして理学療法士として、ずっと向き合い続けているテーマです。
そして改めて感じるのが、行動が変わる瞬間には必ず“理由”があるということです。
それは能力だけでは説明できず、環境だけでも説明できません。
その人の内側で何かが動き、外側との関係性が変わり、初めて「行動」という形で現れます。
〜〜〜
行動変容は、リハビリテーションの本質
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士(PT・OT・ST)の仕事は、単に機能改善をめざすだけではありません。
- 立てるようになる
- 話せるようになる
- 動けるようになる
- 食べられるようになる
これらは“結果”であり、そのためには必ず「何を、どう続けるのか」という行動変容が必要です。
行動科学の研究では、行動変容には以下の3つが重要だと示されています。
- 実行の理由(価値・動機)
- 成功のイメージ(自己効力感)
- 周囲の支援(承認・環境)
これはリハビリに置き換えると、
- なぜ、自分はこれを頑張りたいのか
- うまくいけばどんな未来が広がるのか
- その取り組みは、周囲から支えられているか
という問いにつながります。
この3つが揃ったとき、人は自ら前に進み始めます。
そして、このプロセスに寄り添うのがPT・OT・STの大切な役割です。
〜〜〜
コーチングは、“内側”を動かすアプローチ
では、どうすれば行動変容の3要素をつくり出せるのか。
ここで力を発揮するのがコーチングです。
コーチングを「対話を重ね、柔軟な思考と行動を促し、ゴールに向けて伴走するパートナーシップ」と捉えると、行動科学との親和性は非常に高くなります。
コーチングの特徴は、“問い”を通じて、本人の内側にある力を引き出すことにあります。
- 叶えたい未来は何か
- 必要な行動の最小単位は?
- いま抱えている残念さは?
- 誰にサポートを求められるか?
こうした問いは自己効力感を高め、「やってみたい」「できるかもしれない」という前向きな感覚を育てます。
リハビリ現場でも、問いかけひとつで
- 自主トレの頻度が上がる
- 生活のイメージが明確になる
- 目標が“本人の言葉”に変わる
といった変化が生まれます。
つまり、コーチングは行動変容の“土台”をつくるアプローチなのです。
〜〜〜
チームの行動も変わる。心理的安全性という土壌
行動変容は、患者・利用者だけの話ではありません。
PT・OT・STのチームや、組織全体にも同じことが言えます。
心理的安全性の研究では、安全なチームほど、
- 改善の提案が出やすい
- 失敗を共有しやすい
- 協働が進み、成果が上がる
ことが示されています。
行動変容は、個人の問題であると同時に、組織の文化でもあります。
その文化を支えるのが、次の3つの“つながり”です。
- 人と人
- 人と組織
- 組織と組織
この間のコミュニケーションが活性化し、言いづらいことも安心して話せる環境が整うと、チーム全体が変化に向けて動き始めます。
PT・OT・STは、対話と観察のプロ。
だからこそ、コーチングの視点との相性がとても良いのです。
〜〜〜
行動変容を支える専門職として、これからできること
行動変容を支援できる専門職は、これからの医療・介護現場でますます求められます。
制度が変わり、地域包括ケアが広がり、「その人らしい生活」を実現する力が問われているからです。
その意味では、最近目にすることが多くなっている、産業理学療法などの分野でも必要とされる力です。
技術はもちろん大切ですが、行動変容には技術だけでは足りません。
- 本人がどうありたいのか
- チームがどうありたいのか
- その実現に向けてどんな問いを投げかけるのか
- どんな関わり方で伴走するのか
ここにPT・OT・STとコーチングを掛け合わせる価値があります。
“行動変容の支援”という軸を持ち、
“対話の力”を武器にできる専門職は、これからの現場で大きな存在になります。
リハビリの専門性とコーチングの力で、
その人の未来、そして組織の未来が前に進み始める。
そんな支援が広がっていくことを願っています。
〜〜〜
成長と幸せの輪を対話で広げる
Be a Smileでは、医療・介護・リハビリ分野のリーダーに向けた研修・コーチングを通して、
「対話から始まるチームの成長」をサポートしています。
リーダー研修、職場づくり、講演・動画出演などのご相談は、こちらからお気軽にどうぞ。
👉 お問い合わせフォームはこちら